建設業許可の重要性と許可取得の必要性

- 任せて安心許認可申請
- 信頼の相続・遺言業務
- 初回ご相談は無料です
- 適格請求書対応
建設業許可とは
建設業は国や国民にとっても非常に関係の深い重要な産業です。総じて大きなお金が動きますし、公共事業とも密接に関わってきます。また場合によっては生命や財産に関わる産業でもあります。
そのため建設業を営む業者については、各種の法律によって厳密に資格要件を定めています。特に重要な法律に建設業法がありますが、その建設業法によって「建設業を始めるには軽微な工事のみを行う場合を除き、建設業の許可が必要である」と定められています。
建設業許可が必要となるのは、発注者から直接建設工事を請負う元請負人はもちろん、下請負人として請負う場合も含まれます。これは個人であっても法人であっても同様です。許可を受けずに軽微な工事以外の建設工事を請負うと罰せられることとなります。
軽微な工事とは
建設業許可が不要な軽微な工事とは、次のものをいいます。
- 建築一式工事では、1件の請負代金(消費税等含)が1,500万円未満の工事または延べ床面積が150㎡未満の木造住宅工事。
- 建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事。
軽微な工事の注意事項
- この金額の範囲内での工事のみを施行する場合は、建設業許可を取得していなくても問題ありません。しかしひとつでもこれを超えた工事を請け負う場合には、建設業許可を取得しなければなりません。
- 上記の金額には、消費税等の税も含まれます。
- 分割された請負の場合でも、基本的には分割分を合計した金額となります。合算となるか分割でも良いかは、工事の内容によっては事前に確認されたほうが良いと思われます。
- 注文者から材料等が支給された場合は、それらも請負金額に含まれます。またその際は運搬費等も計算の対象となります。
軽微な工事以外の建設業許可不要な工事
次に挙げる工事については、軽微な工事を超えるものであっても建設業許可は要しません。
- 自らが使用する建築物を自ら施工する場合。
- 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合。
- 土地に定着していない物の工事の場合。
建設業許可を取得する目的
建設業許可を取得する理由には次のような目的があるのではないでしょうか。
- より大きな額の工事を請負い、業務の幅を広げる目的。
- 建設業許可を受けることによって会社の信用力を高め、あわせて営業力を向上させる目的。
- 大手建設業者からの信用力を備えることによって、大手建設業者の下請けとして参入する目的。
- 効果的な資金調達を行うため金融機関からの融資に足る信用力を得る目的。
- 元請として公共工事に参入する目的。
企業コンプライアンスからの建設業許可取得への要請
社会的基幹産業である建設業にも、強い企業コンプライアンスが求められています。
企業コンプライアンスはもともとは広く法令遵守という意味で使われていましたが、現在においてはそれだけではなく、社会的規範や社会倫理等も含むものという広い解釈がなされています。特に大手企業や信用を重んじる業界においては、コンプライアンスに対する認識や社内外へのコンプランスへの対応次第で、社会的信用が揺らぐものとなりかねません。
建設業許可においても、欠格者要件や誠実性要件によってコンプライアンスが担保されていますが、その声は社会的にも、また行政からの要請も高まりこそすれ弱まることはありません。特に建設業においては社会に安心を与える重要性から、下請けを束ねる責任ある大手業者に対しては、コンプライアンス遵守の要請は一層強いものとなっています。
昨今行政からも社会保険への加入要請は強まっておりますが、もちろん大手のみならず、従業者を雇う事務所には軒並み強い要望としてなされております。この状況を鑑み、元請業者自身も自らの責任という観点から、契約する下請け等に対しても建設業許可を有した業者を採用する方向性が明らかになってきています。
下請けの建設業無許可業者に500万円以上の工事を施工させていたとの内容で、元請業者に行政指導がなされるケースが増えているようです。うっかりの場合もあるでしょうが、元請業者にとってはそのうっかりで社名に傷が付く場合もありますので、今後も建設業許可を取得している建設業者を優先的に指名するケースが増えていくものと思われます。
ここのところの人手が足りない、業者が足りないという状況においてもまず優先されるのは、雇用環境も含めてのコンプライアンスという時代であることは否めません。
建設業の許可取得やその維持については、そう安くはない諸々の費用が発生します。しかし現在の状況と今後の展望を鑑み、費用対効果の面も含めて、この機会に建設業許可の取得をご検討されてはいかがでしょうか。
当事務所のお役立ち
当事務所にご依頼いただくメリット
- 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
- 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
- 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
- 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
- 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
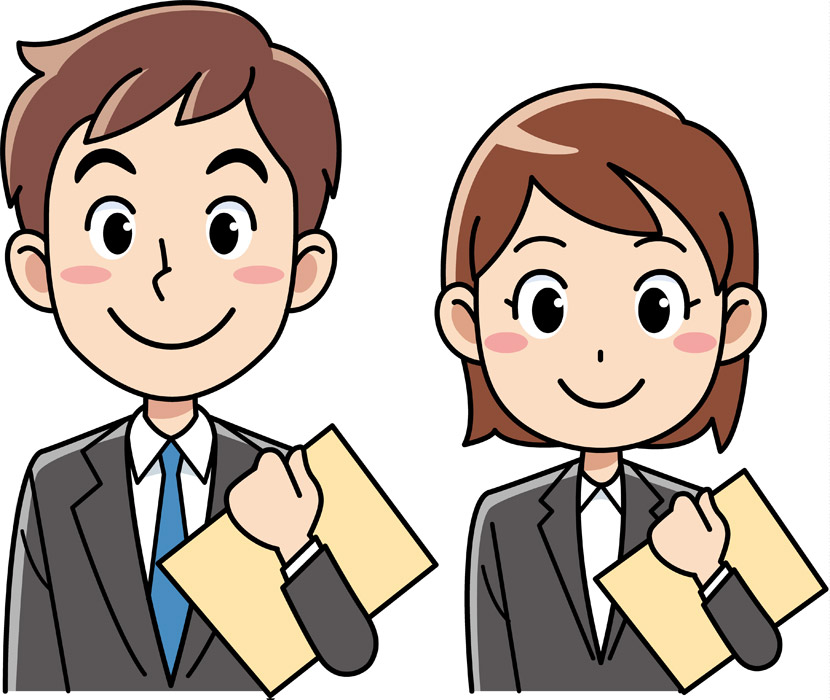
行政書士の仕事と当事務所のお約束
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
- お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
- 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。
書類の作成や文書の作成などは、

- 法律や申請方法を勉強し
- 数々の書類を取得し
- 慎重に書類を作成し
- 平日に役所と交渉をし
- 平日に役所に申請をする
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
行政書士と他士業
- 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
- 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
- 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
高崎市新保町329番地3
高崎インターから5分
℡ 027-377-6089
