相続に関する民法等改正

- 任せて安心許認可申請
- 信頼の相続・遺言業務
- 初回ご相談は無料です
- 適格請求書対応
不動産登記の義務化(2024年4月1日施行)
相続で不動産を取得した相続人は、その相続から(相続により所有権を取得したことを知った日から)3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。また遺産分割協議によって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた相続登記の申請をしなければなりません。正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかったときは、10万円以下の過料の適用対象となります。
同じく2024年4月1日から、より簡易的に相続登記の申請義務の履行ができるよう、「相続人申告登記」という新たな制度が設けられました。この制度の内容は次の通りです。
不動産所有者が亡くなった場合において遺産分割協議がまとまるまでは、全ての相続人が民法上の相続分の割合で共有している状態となります。「相続人申告登記」は、まだ協議がまとまっていない状況において、【登記簿上の所有者についての相続が開始されたこと】【自らがその相続人であること】を申し出る制度です。この申出がされると相続人の氏名・住所等が登記されます(持分までは登記されません)。 ただしあくまで申告義務を果たすというだけの制度ですので、通常の相続登記とは性質が異なります。
相続土地国庫帰属制度(2023年4月27日施行)
相続によって取得した土地でも青地の農地など、利用価値がないのに将来にわたって固定資産税などを負担しなければならないいわゆる負の財産の問題が多くあります。この問題が様々な放棄地や空き地問題を引き起こしていることを鑑み、その土地の所有権を国庫に委譲できる制度が創設されました。この制度が相続土地国庫帰属制度です。
相続土地国庫帰属制度とは、国庫に委譲したい土地(「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分される不要な土地)を委譲法務大臣(法務局)に承認申請し、要件審査を通れば国庫帰属の承認が下りるという制度です。相続したはよいが利用価値がなく、将来にわたって子孫の相続等に影響を及ぼしかねない土地を自分の代で処分しておきたいと思われる方にとっては願ってもない制度といえます。
ただこの制度は手続が面倒なことと、承認された場合にも10年分の土地管理費相当額(おそらく数十万円)の負担金を支払う必要がありますので、申請される場合にはその腹づもりも必要になります。
民法改正の概要(2019年、2020年施行)
相続分野に関する改正民法が可決成立しました。約40年ぶりの大幅見直しとなります。
相続分野の改正法は、一部を除き2019年7月1日に施行されました。例外として、自筆証書遺言の方式緩和(自書以外の目録可)は2019年1月13日に施行され、「配偶者の居住権制度」は2020年4月1日、「自筆証書遺言の保管制度」は2020年7月10日に施行となりました。
詳細は各項で確認下さい。
今回の見直しについてはかねてより問題化されていた、超高齢社会における配偶者への居住権の確保等が主軸になっています。
主な改正点は次のとおりです。
- 配偶者の居住権を保護するための方策
- 遺産分割等に関する見直し
- 遺言制度に関する見直し
- 遺留分制度に関する見直し
- 相続の効力に関する見直し
- 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
配偶者の居住権に関する短期的な保護
配偶者短期居住権制度
配偶者の居住権保護については、短期的な保護と長期的な保護の両面から確保されることとなりました。
現行法では明文化はされていませんが、判例から配偶者の居住権については、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していれば、原則被相続人と相続人の間で使用貸借契約が成立していたと推認され、そのまま居住することができます。
しかし第三者にその建物が遺贈されてしまったり、配偶者が居住することに被相続人が反対の意思表示をしていた場合には、使用貸借が推認されずに居住が保護されないことになってしまいます。
そのような事態を回避すべく、短期的な配偶者保護施策として、配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合について、「配偶者短期居住権」というものが設けられました。
「配偶者短期居住権」制度は、2020年4月1日に施行されました。
次の2通りで保障されます。
- 配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合は、居住建物の帰属が確定するまでの間の期間。ただし帰属が6ヶ月以内に確定した場合でも、最低6ヶ月は保障される
- 居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合には、居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6ヶ月間、配偶者は居住建物を無償で使用する「配偶者短期居住権」を取得する
被相続人の建物に無償で住んでいなかった場合にはこの権利は取得できないことになりますが、権利を取得すれば必ず最低6ヶ月間は居住が保護されることになります。
■遺言書のない相続は大変です。専門家による遺言書作成の指導・代行、相続の執行代行はお任せ下さい
配偶者の居住権に関する長期的な保護
配偶者居住権制度
長期的な配偶者保護施策として「配偶者居住権」というものが新設されました。これは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間の配偶者の建物使用権を認める内容となります。この配偶者居住権は「物件」であり、「登記」することもできます。なお「配偶者居住権」は、登記しないと第三者に対抗できません。
この制度は2020年4月1日に施行されました。
現行制度では、遺言書がない相続でその相続財産の多くが土地建物等の不動産だった場合など、法定相続分の規定によって、配偶者が建物以外の預貯金等を取得できなかったり、あるいは建物を売って共同相続人に金銭を渡さなければならないケースも出てきます。
例えば配偶者とその子供が1人いた場合法定相続分は、配偶者1/2、子1/2(複数いる場合はその子らで等分します)になりますので、相続財産が自宅(土地建物)2000万円、預貯金が2000万円の場合では総額4000万円となり、配偶者が自宅を相続すると預貯金の2000万円はすべて子の相続分となります。
預貯金が1000万円だったとしますと相続合計は3,000万円になりますので、1/2ですと1500万円になり、配偶者が自宅を相続した場合で子から請求があった場合は、子に500万円を支払わなくてはなりません。これでは相続によって配偶者が住む自宅を失いかねません。
それを解決するために設けられた制度が「配偶者居住権」になります。これは相続された自宅を、「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分け、配偶者の自宅の相続額を低く設定する効果が生じます。
先の相続総額4000万円の例で言いますと、配偶者居住権が1000万円とされればその居住権をもって住み続けることが可能となり、残りの負担付き所有権を子が相続した場合には、配偶者の相続額は2000万円ですので、1000万円分の預貯金を相続できるという仕組みになります。子には負担付き所有権1000万円と預貯金1000万円が相続されることとなります。
相続が開始した年齢にもよりますが、配偶者はその先何十年も生きることはないと仮定し、平均余命から割り出した住み続けられる間の価値が配偶者居住権になります。あるいは何年か後には老人ホームに移るので、自宅にはそれまでしか住まない、という選択肢もあるかもしれません。配偶者が亡くなった場合は自宅は子のものとなりますので、それが負担付き所有権となります。
この規定によって、現在の自宅の価値がまるまる配偶者の相続分になってしまい、その他の財産を相続する権利を失ってしまうことから回避されることになります。
配偶者居住権制度の問題点
しかしながらこの「配偶者居住権」には問題点も指摘されています。
- 配偶者居住権の付いた建物の資産価値は当然低くなりますし、いざという時に第三者に売ることができないということになります。配偶者の居住権が付いた家では、市場で買い手がつくはずはありません。
- その家に抵当権が付いていた場合には、居住権との先後の問題もあります。
- 「配偶者居住権」は配偶者の方の終身の権利ですので、その方が亡くなれば権利は消滅しますが、途中で配偶者居住権を放棄する場合(老人ホームなどに移る場合等)は、配偶者から子などに贈与があったとみなされ、贈与税が発生する恐れがあります。
- 固定資産税の支払者を明確にしておく必要があります。
運用面では非常に難しい問題をはらんでいるようですので、実際に「配偶者居住権」が問題になる関係性がある場合には、公正証書遺言を残しておくことが最善策と言えます。
建物敷地の現在価値ー負担付き所有権=配偶者居住権の価値
遺産分割に関する見直し
遺産分割に関する見直しについては次の3つの内容が含まれています。
- 配偶者保護のための持戻し免除の意思表示推定規定の新設
- 仮払い制度等の創設・要件明確化
- 遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
配偶者保護のための持戻し免除の意思表示推定規定の新設
生前贈与の持ち戻し免除
婚姻期間が20年以上であれば、配偶者に居住用の不動産を生前贈与または遺贈した場合でも、原則として計算上「特別受益」(遺産の先渡し)を受けたものとして取り扱わなくてもよい。
現行制度では被相続人が配偶者のためを思って自宅を生前贈与していた場合でも、「持戻し制度」というものによってその自宅は「特別受益」とされ、遺言による「持戻し免除」の表示がない限り、相続財産に合算されてしまいます。
どういうことかと言うと、先ほどの総額4000万円の例で見ますと、現行法では生前贈与された2000万円の自宅も相続総額に含まれることとなります。配偶者の相続分はこの自宅のみとなってしまい、残りの預貯金2000万円はすべて子に相続されることになります。
これでは生前贈与した意図が相続に反映されないこととなってしまいます。今回の見直しでは、20年以上法律上の婚姻期間がある者については、その貢献に報い、老後の生活を保障すべきものとして、「持戻し免除」の表示がなくても表示があったと推定して(被相続人の意思の推定規定)、遺産の先渡しとして扱わずに相続財産総額に含めないことになります。
先の例で言いますと、遺産総額は自宅を含まない預貯金2000万円となり、配偶者と子がそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。
生前贈与のデメリット
- 夫から妻へ住居の生前贈与を行なった場合、不動産の登録免許税が5倍掛かります。通常の相続の場合は不動産の価額×1000分の4ですが、生前贈与の場合は不動産の価額×1000分の20になります。例えば住居(土地+建物)の評価額が2000万円だった場合は、相続なら登録免許税は8万円ですが、生前贈与の場合は40万円となります。
- 相続の場合は不動産取得税は無税ですが、生前贈与の場合は不動産取得税が掛かってきます。
- 生前贈与した不動産も、遺留分侵害額請求の対象となります(贈与から10年で時効)。
仮払い制度等の創設・要件の明確化
一定額の即時払戻しが可能に
現行法では判例から、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金の払い戻しをすることができません。
相続される預貯金債権は相続人全員の共有債権になりますので、それぞれの相続分が確定するまでは生活費や葬儀費用、相続債務の弁済などの必要性があっても払い戻しができず、相続人が立替える必要がありました。
今回の見直しにおいてはこれが緩和され、2つの仮払い制度が設けられることとなりました。
- 預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮処分の要件が緩和されます。従来も訴えにより認められることはありましたが、見直しによって、仮払いの必要性があると認められる場合は他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断(手続き)で仮払いが認められるようになりました。
- 家庭裁判所の判断を経なくても払い戻しが受けられる制度が新たに設けられました。これは相続人としての相続分であれば、そのうちの一定額について単独で払い戻しが認められるという制度です。
相続開始時の預貯金総額×1/3×払い戻しを受ける共同相続人の法定相続分)まで払い戻しが認められることとなります。
相続開始後の共同相続人による財産処分
遺産の使い込みが見逃されない
現行法では特別受益のある相続人が遺産分割前に遺産を処分してしまった場合には、他の共同相続人に不公平な結果が生じてしまいます。例を挙げますと、配偶者がなく子が兄弟2人あったとします。相続される預貯金が2000万円で、長男に2000万円が生前贈与されていた場合には、この贈与分は持戻しとなり、相続総額は4000万円になります。長男にはすでに2000万円が渡されていますので、今回の預貯金2000万円はすべて次男に相続されることとなります。
しかしこの2000万円のうち1000万円分を長男がだまって引き出していた場合には、残りの預貯金が1000万円となってしまいます。すると相続預貯金総額はもち戻しを含めて3000万円となり、法定相続分にしたがって兄弟それぞれが1500万円ずつ相続します。ここでは長男はすでに2000万円を贈与されていますので相続分は0円となり、次男が預貯金総額の1000万円を相続することになります。
これでは長男が贈与分の2000万円と引き出し分の1000万円の合わせて3000万円を受け取ることになり、次男は1000万円しか受け取れず不公平な結果となってしまいます。この場合は裁判に訴えても、結論から言うと次男の受け取り分は本来の2000万円に届くことはありません。
その不公平を是正するために、遺産を処分した者以外(次男)の同意があれば、処分した者(長男)の同意を得なくても処分した預貯金(1000万円)を遺産分割の対象とすることができる、という法律上の規定が加えられることとなりました。
これによって、たとえ共同相続人の一人がこっそり分割前の預貯金を引き出してしまった場合でも不公平が起こらない制度となりました。今の例で言うと、相続財産の総額は4000万円とされ、次男は1/2の2000万円を相続することができます。
この制度は2019年7月1日施行となりました。
遺言制度の見直し
遺言制度の見直しには次の3つの内容があります。
- 自筆証書遺言の方式緩和
- 遺言執行者の権限の明確化
- 法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(民法ではなく遺言書保管法によります)
自筆証書遺言の方式緩和
現行法で自筆遺言に法的効果を生じさせるには遺言書の全文を自書する必要があり、財産が多数ある場合には相当な負担が伴いました。
今回の見直しでは、自書によらないパソコンなどで作成した財産目録を添付することができ、併せて銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付することでも法的効果が生じることとなります。
パソコンなどで財産目録を作成した場合には、財産目録の全ページに署名・押印が必要になります。これがない場合は方式不備で無効となります。
自筆証書遺言の方式緩和(自書以外の目録可)は平成31年1月13日に施行されました。
遺言執行者の権限の明確化
遺言執行者の一般的な権限として、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずる、ということが明文化され、また特定遺贈又は特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における、遺言執行者の権限等が明確化されました。
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設
現行法では自筆証書遺言の管理は遺言者に任されていましたが、見直しによって公的機関である法務局に保管できる制度が創設されました。これは民法ではなく遺言保管法によります。
この制度では相続開始後に相続人が遺言書の写しの請求や閲覧をすることが可能となり(その場合は他の相続人にも遺言書の保管の事実が通知されます)、紛失や改ざんの恐れがなくなることになります。
保管については申請者が撤回することもできます。なおこの制度では現行自筆証書遺言で負担になっている、「検認」の規定は適用されません。
自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月10日施行となりました。
遺言者本人による遺言書保管申請
遺言書の保管等に関する法律についての段取や要件等について記載します。
- 保管の対象となる遺言書は、民法第968条に規定された方式に則って作成された自筆証書遺言のみです。
- 遺言書は封筒に入れずにそのまま持参します(封筒は必要ありません)。
- 保管を申請出来る者は、遺言書の作成者本人のみです。
- 保管の申請が出来る遺言書保管所(法務局)は次のいずれかになります。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局
- 遺言者本人は遺言書の閲覧の請求(内容の確認)をすることが出来ます。
- 保管の撤回もすることができます(遺言書が返却されます)。
- 氏名や住所等に変更があった場合は、変更の届出を行います。
- 相続の発生時(遺言者の死亡時)に、次の者のうち1名を死亡時の通知者として指定することが出来ます。
- 推定相続人(相続人となるべき者)
- 遺言執行人等
- 受遺者等
- 保管期間は120年間です。
- 相続人等は次の交付請求を行うことが出来ます。
- 遺言書の保管有無の確認
- 遺言書の閲覧
- 内容の証明書取得
- 申請を行うことが出来る者は次のとおりです。
- 相続人
- 遺言執行者等
- 受遺者等
- これらの者の親権者や法定代理人(成年後見人等)
- 全国どこの遺言保管所(法務局)でも交付請求を行うことができます。
- 交付請求は相続開始(遺言者の死亡)後に限られます。
- 相続人の一人が閲覧しまたは証明書が発行された場合は、他の相続人に遺言書が保管されている事が通知されます。
- 遺言書の存在確認には、遺言者の死亡が確認出来る戸籍(除籍)謄本、請求人の住民票等が必要です。
- 遺言書の内容証明書の請求には、遺言者の出生からのすべての戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本や住民票等が必要です
- 遺留分侵害額請求(旧 遺留分減殺請求)権から生じる権利を金銭債権化する。
- 減殺請求がなされた場合に、請求された側が金銭を直ちに用意できないときは、請求された側である受遺者などが裁判所に請求することによって、金銭債務の全部または一部の支払いについて、相当の期限を与えられる。
- 遺産分割は現行とおり相続人だけで行われ、それとは別に特別の寄与があった者が相続人に請求を行ないます。これには算出式などありませんので、当事者同士の話し合いになります。また分割協議の成立にも影響を与える制度となりそうです。
- 特別寄与料の目安がなく、額の算定基準があいまい。看護日誌や経費を詳細かつ明確に遺しておく必要がある。
- 特別寄与とはあくまで”特別”な寄与であって、通常の介護やお見舞いに毎日通っていた程度の内容では対象とはならない。
- 特別寄与料の請求期限は相続から6ヶ月以内と非常に短い。
- 家庭裁判所への申し立てを行なう必要があり、これは他の相続人への直接請求をしなければならないため、トラブルが起こりやすい。
- 相続税の2割加算が適用される。
相続人等による遺言書の確認
遺留分制度に関する見直し
遺留分に関する見直しは次の2つの内容からなります。
■遺言書のない相続は大変です。専門家による遺言書作成の指導・代行、相続の執行代行はお任せ下さい。
遺留分の精算は原則現金で行なわれることに
現行法では請求がなされた際にその財産が金銭でなかった場合には、不動産等が現物で精算されることとなっていました。そのため共有状態が生じてしまい、事業承継などの支障になってしまいます。その状況を回避するために、減殺請求された債権は金銭で支払われることを明文化したものです。
減殺請求の支払い猶予について
遺贈などされた財産の額が大きい場合であっても、実際に別途金銭を用意できるとは限りませんので、この内容も加えられています。
相続の効力等に関する見直し
"相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができる"、ことについての見直しとなります。
登記なくして第三者に対抗できるという内容自体は問題ないのですが、相続人の債権者において債務回収の差し押さえなどが発生する場合は、通常法定相続分を想定して計算することになります。ここで遺言によって法定相続分を下回る内容でしか相続されなかった場合は、債権者等の第三者の取引の安全が確保されないことになります。
今回の見直しにおいては、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないと改正されました。
登記されれば債権者もその内容について知ることができますので、取引の安全性が確保されることになります。法定相続分までは現行法とおり、登記なくして第三者に対抗することができます。
逆にここでは大きな問題点も出てくる可能性があります。従来は法律効果のある遺言書(公正証書遺言等)であれば、登記を経ずに相続分を第三者に対抗できましたが、今回の法改正により、法定相続分を超える相続分については、相続登記をしないと先に登記をすませた第三者に対抗できないことになります。ですのでたとえ遺言書によって全ての不動産を長男に相続させると遺言しても、他の相続人が自らの法定相続分を先に登記してあれば、それに対抗することはできません。また他の相続人に債権者がいた場合に、その債権者が相続登記より先に債権者代位によって登記と差し押さえ等を行ってしまった場合は、それに対抗することもできません。
このように、従来は遺言書を遺しておけば相続は万全(遺留分の問題は別として)という状況がありましたが、改正によって必ずしもそうとは言えない問題が生じる場合が出てきました。遺言書の内容が判明した時点で法定相続分を超える相続が発生する方は、前述の内容を考慮して相続登記を急ぐ必要があるかもしれません。
相続人以外の者の貢献を考慮する方策
子の妻等への特別寄与料の創設
相続は相続人にしかすることができません。相続人以外の者には、例えば親身になって世話をしてくれた長男の妻にも相続はなされません。これらの者に財産を贈りたい場合には贈与によるか、遺言書による遺贈や死因贈与の方法をとります。
しかしこの遺言書がなかった場合には、どんなに被相続人に尽くした者であっても、遺産分割協議に加わることはできません。この不公平を見直すべく、「特別の寄与の規定」が設けられました。
これは相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができるという制度になります。親族とは6親等以内の血族および配偶者と、3親等以内の姻族を言います。
この制度は2019年7月1日施行となりました。
特別寄与料の問題点
特別寄与料については基準があいまいなため、問題点を多くはらんでいる
当事務所のお役立ち
当事務所にご依頼いただくメリット
- 相続・遺言は行政書士の得意とする分野です。豊富な経験と専門知識で、ご相談者様の状況に最も良い相続・遺言書をお届けします。
- 相続のトラブル防止を大前提に、関係各所親身になったご提案をさせて頂きます。
- 相続には期限があります。スケジュールに沿った早期安心の解決をお届けいたします。
- 士業のネットワークを駆使し、登記や納税の際もスムーズな連携をお約束いたします。
- 遺言書はその内容が最重要です。侮るなかれ専門家のアドバイスは必要不可欠です。
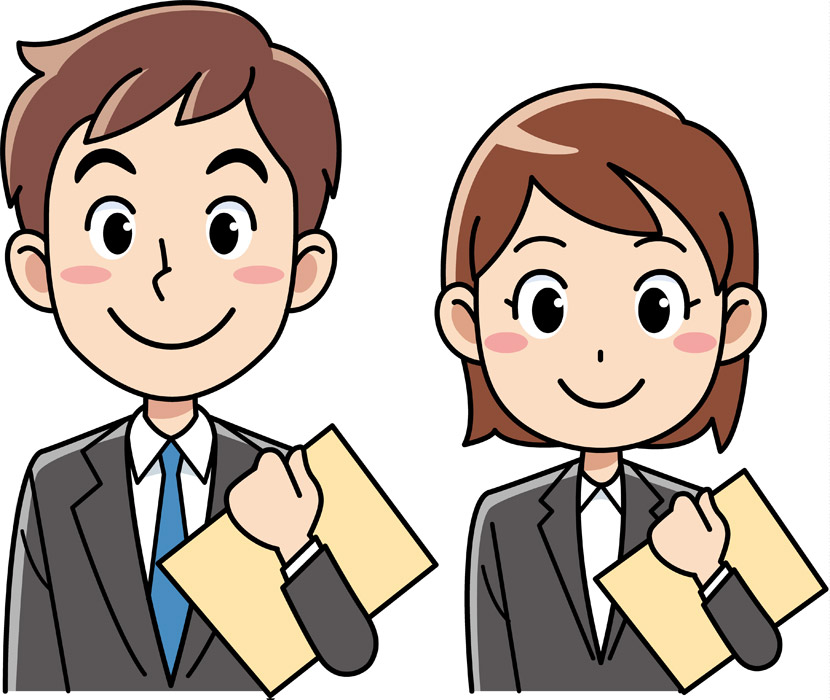
行政書士の仕事と当事務所のお約束
行政書士の仕事は皆様にはなじみの薄い分野が多いですが、平たく言えば、役所への許認可を代理して行う仕事と、文書などを起案作成する仕事が主な業務になります。具体的に言うと、
- お客様の依頼を受けて役所へ提出の書類を取得し、申請書類を作成し、お客様に代理して許認可申請を行います。
- 遺言書や公正証書の文案等を起案作成し、公証役場で公正証書を作成してもらいます。
書類の作成や文書の作成などは、

- 法律や申請方法を勉強し
- 数々の書類を取得し
- 慎重に書類を作成し
- 平日に役所と交渉をし
- 平日に役所に申請をする
このようなことができれば、お客様がご自身で書類を作成したり申請をすることができます。
しかし「許認可申請」といっても、単に形式を満たせば申請を行うことができるものだけではなく、申請書類の内容自体が可否を左右するものであったり、遺言書や相続書類、あるいは契約書などのように、書かれている内容によって質や効果が大きく異なってくるものもあります。
私ども行政書士は蓄えた知識や培った経験から、お客様の事案にもっとも適切な内容を吟味し、最適な形でアウトプットしていきます。
行政書士が報酬をいただいて業務を行うということは、お客様にとって大変な手間や貴重なお時間をお買い上げいただくということになります。
当事務所は知識と経験やネットワーク力を発揮し、打合せから業務終了まで、お客様のご期待に最大限お応えできることをお約束いたします。
行政書士と他士業
- 弁護士はオールマイティです。訴訟の懸念がある相続は弁護士の独壇場です。その分報酬は高めです。訴訟の可能性の低い相続は概して得意分野ではありません。
- 相続税の発生する相続は税理士が得意です。しかし相続税の発生する相続は全体の1割に満たない件数です。税理士の得意分野は税務です。相続税の発生する相続の場合は、税理士とタッグを組みます。
- 司法書士は登記の専門家です。不動産登記は司法書士にお任せします。不動産のある相続は司法書士とタッグを組みます。
ホームページの内容はあくまでも一般的な内容になります。さらに詳しいことを知りたい方は、お気軽にご連絡下さい。

メールで回答させていただきます
行政書士鈴木コンサルタント事務所
高崎市新保町329番地3
高崎インターから5分
℡ 027-377-6089
